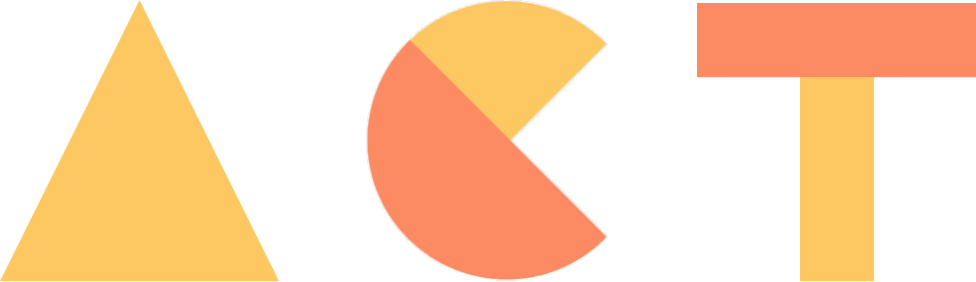概要
| 名称 | 学生団体 Active Council Team(通称:ACT) |
| 英文社名 | Active Council Team(Common name:ACT) |
| 設立 | 2025年5月 活動開始 |
| 代表 | 長尾一成 |
| 所在地 | 大分県別府市内竈APハウス 1 |
| 主な活動内容 | 1.生徒自治活動に関する支援事業 ・生徒自治活動アワードの企画および運営 ・国内外の生徒自治活動の調査および発信 2.課外活動に関する支援事業 ・学生団体やサークルの立ち上げ支援および活動支援 ・ワークショップや文化祭等の運営に関する情報発信や販促促進の支援 ・自己理解塾の運営 3.その他の事業 ・絵本制作やグッズ開発 ・ワークショップやセミナーの開催 ・行政・企業・団体との連携 ・前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
背景
ACTは、メンバー自身の生徒自治や地域活動の経験から生まれた団体です。
文化祭や生徒会で、仲間と衝突し、悩み、時間をかけて合意をつくり出した経験。大学や地域活動で、異なる立場や意見を持つ人と関わり、「分かり合うことの難しさ」と同時に「理解し合えた瞬間の喜び」を味わった経験。
その積み重ねが、「人と人が理解し合う場こそが、安心と成長を生む」という共通の確信につながっています。
将来像(Vision)
人と人が互いを理解し合い、それぞれの個性を力に変えて、協働できる社会を築く。
目的(Mission)
仲間とともに挑戦し、創造を実際に形にする場をつくること。
目標
短期目標:若者が組織を創り運営する機会を広げ、活動を社会に発信する。
長期目標:自己理解と他者理解を深め、協働できる人材を育成する。
活動内容
1.生徒自治活動に関する支援事業
生徒会や委員会などの自治活動を「学びと成長の場」と位置づけ、その価値を社会に広めています。
- 生徒自治活動アワード
-
全国の生徒会や委員会等を対象に、“挑戦や工夫を表彰する仕組み”を企画・運営し、“意思決定や協働の過程”に光を当てています。
- 国内外の事例発信
-
日本全国および海外の自治活動を取材・調査し、その葛藤や創意工夫を記事として発信。他校が学び合える“リアルな知恵”を提供しています。
2.課外活動に関する支援事業
仲間との挑戦は、大きな学びの機会であると考え、学生団体・サークルの運営支援をしています。
- 活動運営支援
-
学生団体やサークルに対し、“立ち上げから運営・会議運営の方法・広報戦略の支援”をしています。継続的かつ自立的な活動展開を可能にすることを目的としています。
関連記事
- 販売支援
-
ワークショップや文化祭等の活動において、“企画内容の検討・発信方法の助言・販売支援を含む包括的なコーチングを実施”しています。
関連記事
- 立ち上げ支援
-
対話を通じて自己理解を深め、「自分はどんなことがやりたいのか」を明確にしていきます。
関連記事
3.その他の事業
世代や分野を横断した取り組みにも挑戦しています。
- 物品・グッツ開発
-
「相互理解」「協働」をテーマに様々な方へ伝わる形で表現しています。
運命の一文 – Words That Moved Me
-
“一言”を通じて「自己理解」と「相互理解」を体感できる機会の提供を行っています。
絵本作成
-
絵本を通して、自己理解と相互理解を体験的に伝え、多様性と協働の意味を子どもと大人の双方に届けます。
-
- イベント等の開催
-
教育・協働・リーダーシップに関する学びの場を設け、幅広い参加者が交流できる機会を創出します。
- 行政・企業・団体との連携
-
外部機関との協働により、若者の活動を社会へつなぐ仕組みづくりを進めています。
なぜ若者?
若者(特に15〜22歳)という年代は、社会的・発達的・教育的に見ても、「自分の行動が社会を変える」体験+成長を最大化できる時期だからです。
人格形成の最も重要な時期
「自分とは何者か」を模索し始める時期であり、“自己理解と他者理解の種が最も深く根づくタイミング”です。この時期の経験や出会いは、その後の価値観・進路・社会との向き合い方を決定づける力を持っていると考えます。
「実践」と「制度」の両方に関われる特別な立場
現実の制度に触れながら自ら動くことができる世代です。仲間と対等に意思決定・対話・創造の経験が積めるのです。
想い (Value)
私たちは、「理解し合う過程にこそ、挑戦と創造の芽がある」と思っています。
仲間と1つの目的に向かうとき、必ず異なる考え方に出会います。
そこで「ああそう考えていたんだ。”私の考え”と”あなたの考え”を組み合わせたら、こんなことが出来るのではないか」「たしかにこの部分は足りていなかった。足し合わせた案を作ろう」。
このように考えると、新しい挑戦・創造が発見できるのではないでしょうか。
一人一人が“特別な飛び抜けた才能”を持っている訳ではありません。
現代の社会では、様々な分野からの視点が重要になっています。
私たちは“人と人が理解し合う過程こそが、最も重要で価値があること”だと信じています。
仲間とともに新たな挑戦・創造をして、実際に行動できる社会が築けるように。
挑戦に意味を、行動に価値を。ACT運営一同