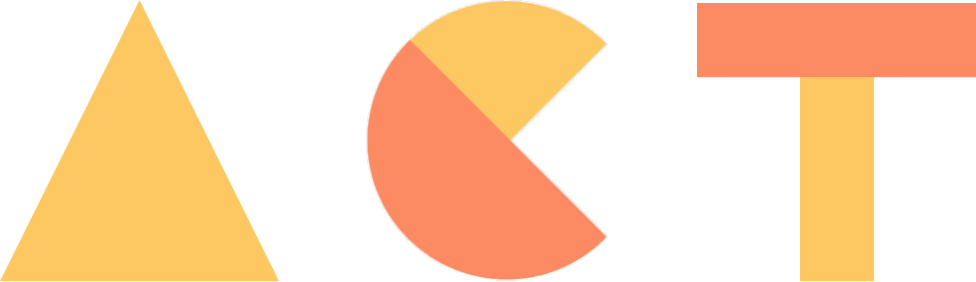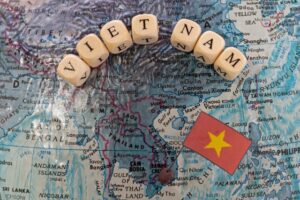「立場と感情の両立を学んだ」Sho Marcellinoさん ― 会長という責任と向き合って
氏名:Sho Marcellino(ショー・マルセリーノ)
出身国:インドネシア
インタビュー形式:書面(翻訳)
内容:生徒会、会長職、意思決定、チームマネジメント
掲載日:2025年5月24日
はじめに:問いから始める生徒自治
「会長」という役職に就いたとき、人はどう行動すべきか。Shoさんは、25人規模の生徒会組織の中で中心的役割を担いながら、「采配」「信頼」「対話」の3つに苦労しながらも学びを深めてきました。
1|組織構造と選抜のプロセス
生徒会は約25人で構成され、コアメンバー4名が全体から選ばれます。選出方法は生徒による投票制。最も支持を集めたメンバーが会長に就任します。このシステムによって、信任された人が責任を負うというリーダーシップ構造が形成されています。
2|活動の設計と運営手法
- 活動領域: 文化行事の企画運営、予算管理、学校内イベントでの商業ブースの出店。
- 予算管理: 賞品や行事準備のための予算を活用。行事当日の売上も次年度予算に活かされる。
- 意思決定構造: 会長が最終的な決定権を持ちつつも、メンバー間でデメリットや懸念を共有しながら合意形成を図っている。
3|象徴的な事例と制度的工夫
生徒にとっての“リフレッシュ”を目的に、学業から解放される「Swipe(勉強しない期間)」を提案・実施。お祭りに合わせて商売ブースも出店し、生徒の創造性や責任感を育む機会として位置付けられました。会長という立場から、他のメンバーに業務を割り振ることの難しさも痛感したといいます。
4|困難とその捉え方
「信頼して任せる」という理想と、「自分でやった方が早い」という現実の間で揺れながらも、Shoさんは少しずつチームへの仕事分担を実践。感情の衝突を避けずに、率直に向き合うことが、チームの信頼を育むと気づいたそうです。
5|展望:理想の自治へ向けて
今後Shoさんは、より誠実で率直な対話を通じて、チーム内に「本音で動ける信頼関係」を築きたいと話します。リーダーとしての権限ではなく、関係性の中でリーダーが自然に機能するチーム文化を目指しています。
6|教育的意義と他校への示唆
この事例は、制度やルールに依存するのではなく、「信頼」と「真摯な関係性」によって組織が成立するモデルです。責任を他人に預けず、行動で信頼を築く姿勢は、どの学校にも応用可能なリーダーシップの原型といえるでしょう。
編集後記
Shoさんの言葉からは、実務能力だけでなく、「人間関係の難しさと向き合う覚悟」がにじんでいました。生徒会を通じて、ただの役職ではなく「文化をつくる」存在へと変わっていく姿が印象的でした。
※掲載にあたり、ご本人の同意を得ています。
※お問い合わせ:office@act-jp.org