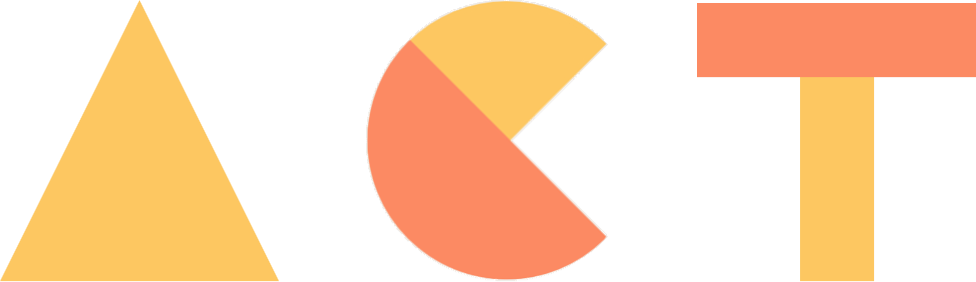ACTのビジョンに根ざして
ACT(Active Council Team)の最終的なゴールは、 【人と人が互いを理解し合い、その違いを力に変えて協働できる社会を築き、持続させていくこと】 です。その実現に向けて【若者が自己理解と他者理解を深め、仲間とともに挑戦や創造を実際に形にする場を創ること】を目的としています。( 関連リンク:ACT-団体概要 )
アワードにおける目的
生徒会・委員会等の自治活動を、公開された審査基準に基づく第三者評価と称賛・フィードバックによって可視化し、当事者である若者の社会的信頼を高めるとともに、活動の継続・拡張・連携を生み出す環境を構築することを目的とする。
方針
学生にとって
- 挑戦や工夫が社会に認められる経験になる。
- 授与される表彰状は、総合型選抜(AO)や推薦入試等の実績として活用できる。
後援・協賛 団体にとって
- 人材育成への参画:次世代リーダーの成長に関わる。
- 社会貢献・PR:学生支援の姿勢を社会に発信。
社会にとって
- 若者の主体性・協働を評価する文化が広がる。
- 民主的な対話に基づく持続可能な社会の基盤が強化される。
特徴
- どこかの地域に遠出せずに評価される
- 公開審査、評価基準が明確で結果に納得
- 活動証明書を発行
背景と課題(データ)
自治活動(生徒会・委員会など)は、課題発見・対話・意思決定を伴う学びの宝庫です。しかし、 活動の形式化、参加率の減少、社会発信の不足といった課題が各種調査・審議会資料で指摘されています。それらは、公正な評価機会の不足により、努力や挑戦が“見えにくい”ことが一因だと考えました。
形式的な活動と見なされがちな現状
生徒会・委員会が「行事運営の準備役」に限定され、 本来の民主的な意思決定の訓練の場として十分に機能していない現状が指摘されています。
(参考:文部科学省(2015)『特別活動について』中央教育審議会)
参加率の低下問題
生徒会活動に主体的に関わる生徒は減少傾向にあります。
(参考:文部科学省(2016)『特別活動ワーキンググループにおける審議の取りまとめ』)
地域・社会と接点が少ない
自治活動は社会参画の入口であるにもかかわらず、地域・社会との接点が限定的です。 校外発信が少なく、活動の社会的意味づけが希薄になっています。
(参考:文部科学省(2014)『社会教育に関わる地域人材の養成実態及び活動実態に関する調査研究』)
※詳細な数値・図表は出典の各資料をご参照ください。
なぜ「アワード」という形式か
- 社会的承認:表彰=“活動に重みと継続の動機”を与える。
- 公平性と透明性:審査基準を明示し、応募された文章をそのまま公開。
- 次の挑戦へ:社会に認められる経験が、学生と学校の次の改善・創造を後押し。
目標について
短期目標
若者が組織を創り運営する機会を広げ、活動を社会に発信する。
長期目標
対話と協働を通じて社会に新しい価値を生み出す人材を育成し、違いを力に変える協働社会を持続させる。
生徒自治活動は、その未来を実現する有効な「場」の一つです。アワードは、その価値を社会とつなぐための仕組みです。
2025年度スケジュール
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 6月~7月 | 第1期応募・審査(8月上旬 発表) |
| 2月~3月 | 第2期応募・審査(4月上旬 発表) |
関連リンク
- ACT ホームページ:https://act-jp.org/
- 生徒自治活動アワード:https://act-jp.org/award/
- 日本国内の生徒自治活動:https://act-jp.org/category/japan/