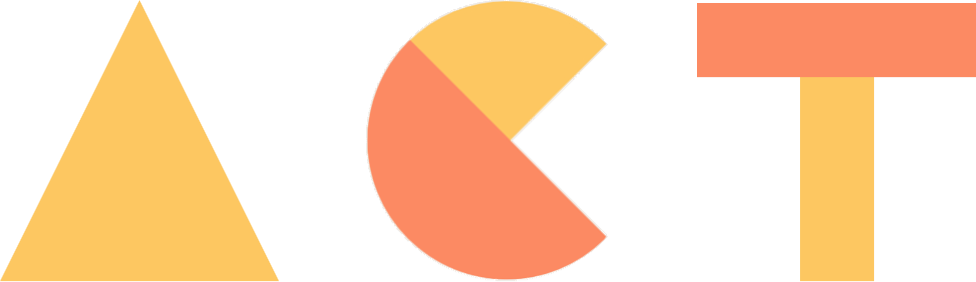結果発表
最優秀賞(89点)
| 都道府県(例:○○都、北海道、○○府、○○県) | 滋賀県 |
| 学校の郵便番号(例:〒100-8111) | 〒524-0051 |
| 学校の住所 | 滋賀県守山市三宅町250 |
| 学校の正式名称 | 立命館守山高等学校 |
| 活動年月(例:2023年4月~2024年3月) | 2022年4月〜現在 |
| 所属団体名 (生徒自治会・文化祭実行委員会などを記入) | ルールメイキング委員会 |
| 活動したメンバーの氏名(2名以上) |
| 米田圭吾、中北啓 |
校則改正までの過程が明確に示されている点を高く評価した。どの学校でも一度は議論になる話題であるが、実際に実現をしたという話はあまり聞かない。これは校則改正の手順模範例となるだろう。アンケートを実施するところまでは多くの学校で行われてきたが、生徒だけでなく先生へのアンケート、試用期間の提案などから、先生と生徒が対等な立場で対話を行なってきたことが読み取れる。争いを避け、プロセスを明確にし、議論を続けた彼らの姿勢は、校則以外の議論でも理想と言える立ち回りであろう。
優秀賞(82点)
| 都道府県(例:○○都、北海道、○○府、○○県) | 滋賀県 |
| 学校の郵便番号(例:〒100-8111) | 〒524-0051 |
| 学校の住所 | 滋賀県守山市三宅町250 |
| 学校の正式名称 | ⽴命館守⼭中学校・⾼等学校 |
| 活動年月(例:2023年4月~2024年3月) | 2025 年 1 ⽉〜025 年 5 ⽉ |
| 所属団体名 (生徒自治会・文化祭実行委員会などを記入) | ⽣徒会執⾏部(体育祭実⾏委員会) |
| 活動したメンバーの氏名(2名以上) |
| 渡邉幸⼤朗、 今村聡 |
今まで一方的であった体育祭の運営に生徒を巻き込み、対話の場を設けたことを評価した。委員会に所属する生徒のみならず、全校投票などの手段を駆使し、全生徒の意見が反映される場を創ったことは、体育祭運営の模範と言えるだろう。グラウンドでのポンポン・モールの使用の可否について、具体的な過程が記されており、生徒を巻き込んだ議論がされていることが読み取れた。持続性の点において、資料の形式を統一し保管することは重要であるが、少しありきたりなように思われる。あともう一歩工夫がなされていればより模範的であると感じた。
優秀賞(27点)
| 都道府県(例:○○都、北海道、○○府、○○県) | 東京都 |
| 学校の郵便番号(例:〒100-8111) | 〒114-0015 |
| 学校の住所 | 東京都北区中里3−12−1 |
| 学校の正式名称 | 聖学院中学校・高等学校 |
| 活動年月(例:2023年4月~2024年3月) | 2023年4月〜2025年3月 |
| 所属団体名 (生徒自治会・文化祭実行委員会などを記入) | 聖学院高等学校生徒会 |
| 活動したメンバーの氏名(2名以上) |
| 遠藤至恩(前会長)、永井健太(会計)、橋本優(議長) |
外務活動に焦点を当て、何を考え、どのように改革を行なってきたのか細かく示した点を評価した。筆者が他校の活動から刺激を受け、自校の反省点を炙り出し、現状を見つめ直した事が読み取れた。筆者の考えはとても魅力的であるように思えたが、具体的な活動が弱いように感じた。生徒会活動をInstagramなどを駆使し透明化したことは評価できるが、本文中に明記されていたVISION130の内容がより具体的であって欲しかった。おそらく筆者は外務活動から多くの刺激を受け、芯のある考えを持っていると思われるからこそ、より具体的な改革を進めていけるはずである。
総括
今回初の試みとなった本アワードである。ただ、広報・周知の過程に大きな欠陥が見られた。生徒会・委員会が評価される場が少ない点に着目し、活動の価値を社会に示す機会を増やそうとこのアワードを開催したことは、評価されるべき点である。しかしながら、他団体にて行われている同様のイベントとの大きな差別化が図れていない点でアワードを開催した点については反省する点が大きい。
1点目について、部活の大会が多くあるように、生徒会の評価の場も多くあるべきだという考えから開催されたアワードという風に聞いている。その点は賛同するが、評価方法を審査員ではなく全国の役員の投票で決めるなど、他団体との大きな差別化を図るべきであった。審査員の中には、他団体の大賞に応募したことがある人がおり、長い応募文を作成することが大きな障壁であったと言っている。他の生徒会業務も忙しい中、長い応募文を必要とするアワードは障壁となる。
2点目について、先ほど述べた障壁にも繋がるが、自分自身にメリットが無いものに長い時間を費やそうとは思わないだろう。発足したてでメリットのよくわからない団体には応募する可能性が低くなると考える。
生徒会・委員会活動を評価してもらいたいというニーズに応えようとしたことは素晴らしい。その一点のみならず、SNSなど学生の目につきやすい場所で知名度をつけること、学校や他の団体との連携を図ることなど、もっと広い視野で学生のニーズに応えるべきであると考える。