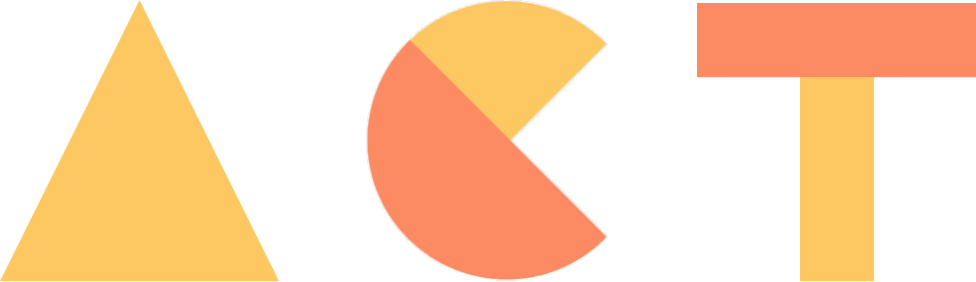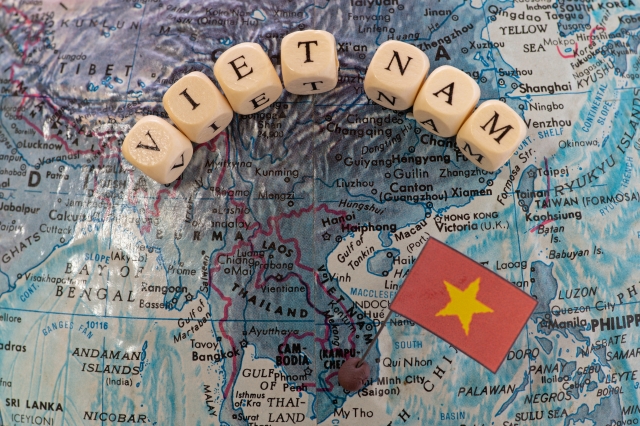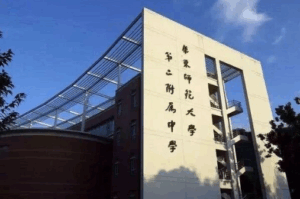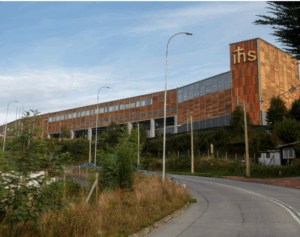「楽しさと責任のバランス」Linhさん(ベトナム)― 学内文化を創る主体としての挑戦
氏名:Linh(りん)
出身国:ベトナム
インタビュー形式:書面(翻訳)
内容:生徒会(自治組織)
掲載日:2025年6月16日
はじめに:問いから始める生徒自治
「生徒会は単なる役職か、それとも文化の担い手か」。学業優先の価値観が強いベトナムにおいて、Linhさんは「楽しむこと」と「制度的責任」の両立を模索しながら、生徒自治の新しい形を実践してきました。
1|組織構造と選抜のプロセス
生徒会は約100人で構成され、希望者が立候補し、面接を経て各部署に配属される仕組みです。積極的な生徒は少ないものの、立候補者は基本的に全員参加可能で、各部署にはリーダーが置かれます。一方で、生徒会長のような全体を束ねるポジションは存在しません。
2|活動の設計と運営手法
- 活動領域: 校内でのオープンスクールイベントやコンサート企画。主に入学希望者向けの学校広報活動を担う。
- 予算管理: 予算の50%以上をイベントに使用し、必ず余剰金を残すよう設計。翌年度に繰り越し、市や企業からの支援も受けている。
- 意思決定構造: 部署単位での小規模な意思決定体制。意見の対立は少なく、発生してもカジュアルな対話によって円滑に解決される。
3|象徴的な事例と制度的工夫
「オープンスクールの自律運営」と「予算繰越制度」は、Linhさんの生徒会の中でも象徴的です。特に校内コンサートを定例化し、広報と楽しさを両立する施策は、生徒にとっても学校にとっても成果の大きな企画となりました。
4|困難とその捉え方
複数の部署リーダーが強い権限を持つ一方で、生徒会全体の統一感に欠ける点が課題でした。また、校外への発信力が弱く、活動の意義が限定的に捉えられやすいというジレンマも抱えていました。
5|展望:理想の自治へ向けて
Linhさんは「明確なリーダーシップと制度的支援の融合」を目指しています。生徒会長職の設置、顧問教員の導入などによって、現在の自由な雰囲気を保ちつつも、より安定的な自治体制を築きたいと語ってくれました。
6|教育的意義と他校への示唆
「楽しさ」を起点にした自治体制は、活動に対する参加のハードルを下げつつ、一定の制度的枠組みの中で成果を出す柔軟な仕組みと言えます。日本の高校においても、サークル的自由と制度的自治を横断するアプローチとして活用できるヒントがあります。
編集後記
Linhさんの取り組みからは、自治という概念が「ルールを守るため」ではなく、「学校を文化として創るため」の装置であることが伝わってきました。自由な空気の中にも規律を宿すベトナムのスタイルは、日本の生徒自治にも新たな視点を与えてくれます。