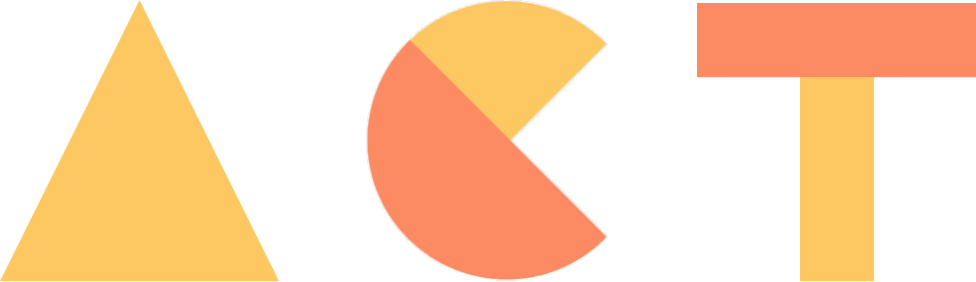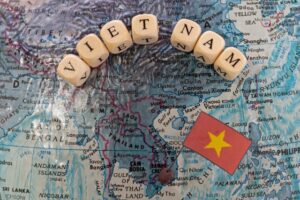「Student Government」が育てる生徒と進路接続
「生徒会」「委員会」と聞いて、日本の教育関係者がまず想起するのは、「行事の準備」「備品の管理」「広報活動」などの“手伝い”かもしれません。しかし、それだけではありません。生徒自治活動は本来、自ら考え、他者と協働し、意思決定するプロセスを経験する場です。
今回は、アメリカの生徒自治活動「Student Government(スチューデント・ガバメント)」の事例を通じて、“教育的価値と進路選択”などについて紹介します。
◆ Student Governmentとは?:日本との違いと概要
- 議会型構造(President, Vice President, Treasurerなどの役職が存在)
- 全校投票による選挙制度
- 学校行事だけでなく、予算配分、政策提言(学校内だけじゃなく、州や市町村へ向けて)、制度改善に関わる
- 学校側との定例ミーティングや、生徒の声の代表としての発言権がある
アメリカの公立高校の約80%で導入されており、広く定着しています(Empowerly, 2022)。
◆ どんな活動をしているのか?:具体例と目的
【1】イベントの企画・運営
例:ホームカミング、プロム、Spirit Week、スポーツ大会など
目的:学校の一体感を高める。生徒主導で文化をつくる経験を通じて、企画力・リーダーシップ・予算管理能力などを育成。
【2】予算の編成とクラブ支援
例:クラブ活動への資金配分、助成金制度の設計など
目的:公共財の分配という民主主義の基本を実践。限られた資源をどう分け合うかを考える機会。
【3】制度改善・提言活動
例:制服の緩和、ランチの改善、休憩時間の延長など
目的:自分たちの学校を「より良い場」に変えていく当事者性を育てる。教員との対話・交渉力も向上。
【4】地域・社会との連携
例:地域清掃、チャリティイベント、社会問題への啓発活動など
目的:自校の外にも目を向け、「市民性(Civic Engagement)」を育成。
【5】選挙と政治参加の練習
例:立候補演説、公開討論、全校投票など
目的:民主的な選挙文化を学校内で体験することで、政治参加の土台をつくる。
◆ 教育的意義:なぜこれが“学び”なのか?
Student Governmentは以下のような資質・能力を育てる場となっています
- 市民性
- 公共性・合意形成力
- 交渉力・実行力
調査によると、「学生の声が尊重された経験がある生徒」は、投票行動にも積極的であるという結果があります。例えば、Tufts大学CIRCLEの研究によれば、そうした生徒の81%が「選挙で投票する意思がある」と回答し、尊重されなかった層では44%にとどまりました(CIRCLE, 2023)。
◆ 日本社会の課題を解決できるのでは
日本では「若者の投票率の低さ」が課題とされていますが、その背景には「投票によって何かが変わる」という実感の欠如があります。学校という小さな社会の中でこそ、生徒が“自分の一票で学校が動いた”と感じられる経験が必要です。こうした体験が、将来の政治参加や社会参画への第一歩となります。
アメリカにおける「自治活動の評価」制度
◆ 進路との接続:アメリカ大学が見るポイント
多くのアメリカの大学では、「Student Government(生徒自治活動)への参加やリーダー経験」は進学時に評価されます。
- Leadership Experience(リーダーシップ経験)
- Initiative(主体性)
- Civic Engagement(社会参画)
これらは、Holistic Review型(ホリスティック・レビュー入試=総合型選抜)の大学入試における重要な評価項目であり、Student Government(=生徒自治活動)の経験は「学力以外の強み」として活かされるのです。
◆ 具体的な評価制度
アメリカでは、生徒自治活動(Student Government)が単なる校内活動ではなく、制度的に評価される仕組みが存在します。以下はその代表的な例です。
National Council of Excellence(NCOE)
全米中高の生徒自治組織を対象に、優れた運営・リーダーシップ・地域貢献・民主的プロセスなどの観点から表彰する制度。
- 全米生徒会協議会(NatStuCo)が主催
- 活動内容をポートフォリオ化し、校長との連携を経て提出
- 基準を満たした団体に「ゴールド/シルバー認定」が授与される
ASCA School of Excellence Award
小中学校を対象に、市民性の育成・コミュニティサービス・協働学習の実践を評価する賞。NAESP(全米小中学校校長協会)と提携。
- 年1回募集、申請書と活動記録を提出
- 学校全体での育成環境も含めた評価
評価される主な観点
- Leadership(リーダーシップ):組織の運営、意思決定、役割分担の工夫
- Civic Engagement(市民性):地域との連携、社会課題への取り組み
- Organizational Impact(組織的成果):制度改革や他生徒への波及効果
- Documentation(記録と振り返り):年間報告、ポートフォリオの質
これらの表彰制度は、生徒自治活動が「学びの成果」として社会から正当に評価されることを意味し、進路や奨学金申請における強力な実績にもなっています。
日本の生徒自治活を振り返って
◆ ACTの役割
ACTでは、こうした海外の事例を活用し、以下の取り組みを進めています
- 生徒自治活動を「評価される経験」に変える仕組みづくり
- 大学入試(総合型選抜など)への接続支援
- 顧問・教員の支援体制の整備(外部顧問制度など)
◆ おわりに:自治は教育の“実験室”である
生徒自治活動は、生徒が「社会の一員として考え、動く」力を育てるリアルな場です。海外の事例に学びつつ、日本でも自治・協働・対話を軸とした教育文化を根付かせていくことが、これからの教育に求められています。