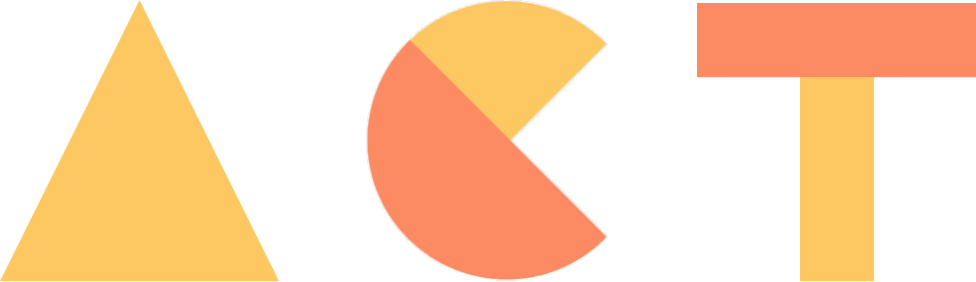聖学院高等学校/生徒会/2023年4月〜2025年3月

目次
| 都道府県 | 東京都 |
| 学校の郵便番号 | 〒114-0015 |
| 学校の住所 | 東京都北区中里3−12−1 |
| 学校の正式名称 | 聖学院中学校・高等学校 |
| 活動年月 | 2023年4月〜2025年3月 |
| 所属団体名 | 聖学院高等学校生徒会 |
活動内容
| 活動タイトル |
| 高校生徒会本部による他校生徒会交流活動 |
| 活動概要 |
| 本活動は、生徒会交流会の開催および参加を基調とした、高校生徒会本部における外務活動である。目的は、「他校生徒会との関係性を広げつつ、内・外部ともに開かれた生徒会を目指す。また、相互刺激による両校生徒会の組織力向上と、他校の視点を得て自校・生徒会・自身の在り方を再確認し、再定義する機会を持つ。」と位置付けている。かつての生徒会活動は、新型コロナウイルスの流行期以降、学校自治のための組織というより文化祭や体育祭などの学校行事の運営に留まるばかりで、生徒会の存在意義が形骸化している実態があった。加えて、生徒会活動としての引き継ぎもなされておらず、活動内容も目的も見出せない状態が長く続いていた。そこで、まずは生徒会活動の透明化を図り、生徒会新聞の発行やInstagramの開設から生徒会の存在を内・外部共に広めていった。そんな中で、InstagramのDMにて他校から「生徒会交流」のお誘いを受け、ここで初めて生徒会役員が他校を知ること、外に出ることの重要性を感じた。それからは、他校の視点を得て次々と見え方が変わる自校の特徴や生徒会活動のあり方に関する考えを基に、学校づくりのための生徒会組織の改革(組織力向上)に取り組むことを2年間でおこなった。 |
| 活動の特徴・工夫した点 |
| 「他校を知ることで、自校を知る」ということが本活動の最も重要となる主題であった。数々の他校生徒会を交流し、それぞれの学校文化や校風を知る。それと比較して、自校の現状分析や新たなる課題を発見し、そこに生徒会の存在意義や次なる使命を見出す。まさしく、本活動は、これからの生徒会活動の内容や目的を定めていくための、「メタ思考の訓練」であった。メタ思考を得るには、他者との関わりが全てである。自己や自身の思考を客観的に見直し、その前提を捉え直す作業は、言い換えれば、他者の視点を知ることと対話である。その作業に終わりはなく、正解もない。だからこそ、継続的な他者との交流を持つことが、自己の成長とより洗練された自分軸(思考や価値観)の形成に繋がる。澤円の『メタ思考 「頭のいい人」の思考法を身につける』では、このような文章がある。『いずれにしても、「外」の世界を知らなければ、自分がとらわれているものを客観的に見て、自分にとってそこにいることが幸せなのか否かをはっきりと認識することはできないのです。』人は、自らの属する環境や価値観を「当たり前」として受け入れがちである。しかし、それが本当に自分にとって望ましいものなのかを判断するには、異なる視点が不可欠である。外の世界を知ることで、自身が何にとらわれているのかを客観的に捉え、自らの幸福について明確に認識することが可能となる。他者の価値観に触れ、多様な選択肢を知ることは、思考の幅を広げるだけでなく、自身の立ち位置を再考し、主体的に生きる契機となる。外を知ることは、単なる知識の拡張ではなく、自らのあり方を見定めるための本質的な営みである。つまり、生徒会役員も同様である。私や私たちは学校においてどうあるべき存在なのか。その探求は、内部にいるだけでなく、外部の視点を知ることでより明確になっていく。他者の例を知ること、多種多様な思考様式に触れることが、現状を見つめ直す機会となるのだ。ゆえに、本活動を通して自校において私たちがなぜ必要なのか、それを検証し、最終的な答えを見出そうと試みてきたのだ。そして、導き出された答えは、他校の視点を得たことによる、自校の再評価、自校生徒の再評価を全校生徒に広め、所属意識を高めることによる生徒自身のモチベーション向上を図り、それぞれの諸活動の推進を間接的にサポートすることであった。生徒が主体的に、自由にやりたいことができる「Only One」教育の校風において、実はあまり厳しい校則や私たちを縛り付けるような伝統は存在しない。時代と共に、私たちは変わってきたからだ。ゆえに、私たちがすべきことは、既にある「良い状態」を、さらにその質を高めていくことであると気づけたのだ。 |
| 実現できたこと、できなかったこと |
| 他校の視点による自校と生徒の評価を広める。そのために、生徒総会にて「他校生徒会交流活動の報告」をしたり、文化祭にて「生徒会活動報告」という展示をしたりしてきたが、当初の目的である「所属意識を高め、生徒のモチベーション向上を図る」ということの効果については、あまり実感できていない。おそらく、伝える機会があまりにも少ない、その伝え方にも問題があるのだろう。ただ、Instagramの投稿は欠かさずおこなっており、外部への生徒会の認知度は高まりつつあると感じている。その点で言えば、最初に述べた「生徒会活動の透明化」は、半分達成できているだろう。こうして振り返ってみると、他校との交流回数は多いものの、その収穫をうまく処理できていない現実がある。実際、生徒会の引き継ぎに関して、新人の当選が昨年は圧倒的に多数であったため、生徒会活動の基礎から教えることに時間を割いている。そこに他校から得た視点やノウハウの教養はまだ早いと考えている。つまり、これからの課題は、他校交流で得た収穫を落とし込み、生徒会活動の明確な目的と具体的な方針を定め、それを全校生徒や教職員に広めていくことだろうと思う。だが、全く0から始めるというわけではなく、既に1つ仮の構想ができている。それは、『VISION 130』。創立130周年までの理想の学校像の策定と実現を目指すための、構想を定めようとしているのだ。生徒たちが社会の創造ばかりに注目がいくのではなく、社会の一つとしての学校の創造に挑めるように、生徒会の本来の目的である学校内民主主義を目指して、今後も励んでまいりたい(現役をサポートしつつ、生徒として)。 |
組織について
| 組織体制(人数、部署) |
| 高校生徒会本部は、会長、副会長、会計、書記の4名と、議長2名、執行委員4名の合計10名で構成される。現在は、会長、副会長、会計、議長、執行委員、執行委員の6名体制で活動している。高校生徒会憲法に記されている役職はこの通りであるが、実際の役割として「内務、Project Manajer、ICT・PR、総務」の4つの役割を設けている。なお、今年度は特別に前年度からの引き継ぎと指導のための「Mentor」を、前生徒会長が務めている。 |
| 任命方式(選挙システム、または希望制なのか) |
| 高校1年性を対象とする高校生徒会選挙は、毎年11月末に行われ、生徒総会の時間中に「立会演説会」をもって立候補者がそれぞれ演説し、その後全校生徒が各HRにて投票する。すべての選挙の運営は、選挙管理委員会が行い、開票結果は翌日に公開される。新役員は、12月1日から任期が始まり、翌年11月末をもって任期満了とする。なお、新高校1年生は、新年度4月に補欠選挙を実施し、紙での所信表明文を通じて全校生徒が投票する形を取る。立候補に関しては、高1・高2生徒であれば、誰でも自由に立候補することができる。なお、定員数を満たない場合は欠員として、定員数をオーバーする場合は決選投票で決着をつける。 |
| 「顧問/学校」と「生徒自治活動の組織」との関係 |
| 評価(1~5点) | 3点 |
| なぜその評価になるのか | 生徒の主体性を重んじる「Only One」教育は、自分らしさを用いて社会貢献をしようとプロジェクトを立ち上げたり起業したりする生徒が多いが、学校教育に関心を持つ者は少ない。特に、従来の生徒会活動が学校行事の運営であったことから、学校生活におけるルールの策定や指導において、生徒会が積極的に関わる機会がないため、50% / 50%の3点とした。 |