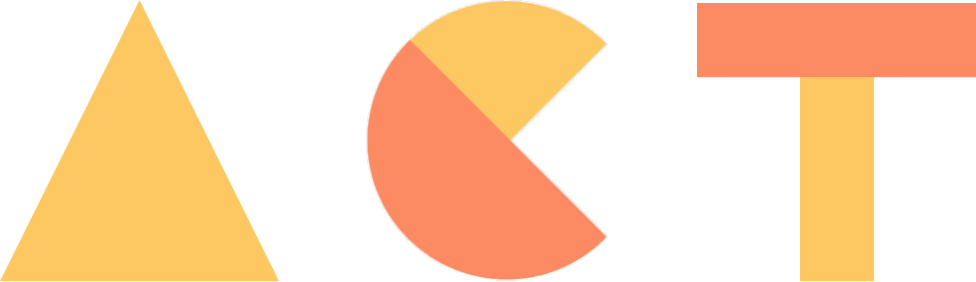目次
生徒自治活動アワード / 最優秀賞 / 2025年第1回
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 学校の郵便番号 | 〒524-0051 |
| 学校の住所 | 滋賀県守山市三宅町250 |
| 学校の正式名称 | 立命館守山高等学校 |
| 活動年月 | 2022年4月~現在 |
| 所属団体名 | ルールメイキング委員会 |
活動内容
| 活動タイトル |
| 「自分たちの学校は自分たちでつくる 〜対話からはじまるルールメイキング〜」 |
| 私たちの学校には、髪型・髪色・ピアス・服装など、外見に関する校則が数多く存在していました。しかし、それらのルールがなぜあるのか、その目的や意図が十分に説明されることはなく、「先生に怒られるから守る」という受動的なルール意識が広がっていました。実際に、校則に違和感を持ちながらも「どうせ変わらない」とあきらめている生徒や、「意味がわからないまま従っている」生徒も多くいました。 この状況に対して、「私たちはもっと主体的に学校をつくれるのではないか」という思いを持った生徒が集まり、ルールメイキング委員会が発足しました。きっかけは、学校の「生徒主体」を掲げた方針でした。せっかく掲げるのであれば、単なるスローガンではなく、実際に私たちの声が学校づくりに反映される仕組みが必要だと考えました。 「ルールは、誰のためにあるのか?」 「そのルールは、生徒の尊厳を守っているのか?」 「ルールを変えることは、どこまで可能なのか?」 こうした問いから活動がスタートし、私たちは校則の見直しを通して、単なるルール変更ではなく、「自分たちの声で学校が変わる」という実感を全校生徒と共有することを目指しました。単なる反抗や自由化を目的とするのではなく、対話と合意形成を通して「納得できるルール」を自分たちの手でつくる文化を根づかせることを目標に活動を行ってきました。 |
| 活動の特徴・工夫した点(具体的な内容) |
| ① 「疑問」から始める校則対話 校則の問題点を「不満」ではなく「疑問」として捉えることで、誰でも安心して声を出しやすくなるよう工夫しました。Googleformで実施したアンケートでは、「なんとなく納得できない」「理由が分からないまま従っている」など、校則に対する率直な声が数多く集まりました。数字だけでなく、そうした生の声を材料にしたことで、次の対話の質が大きく向上しました。 ② 生徒・教員が対等に話す「対話の場」の設計 アンケートで見えた課題をもとに、教員と生徒が一緒に意見を交わす対話会を開催。議論ではなく「対話」を重視し、「なんでそう思うのか」「どうしたら不安が減るか」など、背景にある価値観や思いを丁寧に言葉にしていくよう促しました。参加した教員からも「生徒の視点にハッとさせられた」という感想が寄せられ、立場を越えてルールを考える機会となりました。 ③ 校則の背景を知るために「教員インタビュー」 校則の中には、私たちから見て不合理に感じるものもありましたが、「なぜそのルールがあるのか」をまず知るために、長く勤務している教員にインタビューを実施しました。「過去にトラブルがあったから」「他校とのバランスを見ている」など、生徒だけでは見えなかった背景事情が明らかになりました。このプロセスを通して、私たち自身も「ただ自由にしたい」という姿勢から、「どうすれば納得できるルールに変えられるか」という視点へと変化していきました。 ④ 「試行期間を設ける」案の提起とその壁 提案した新ルール(ピアスの容認や髪色の自由化など)に対して、いきなりの全面実施は現場に不安があると考え、「まずは1ヶ月だけ試してみる」という“試行期間”の導入を検討しました。この案は教員側との話し合いの中でも一定の理解を得ましたが、制度的な課題や判断体制の整備が追いつかず、実施には至りませんでした。それでも、「段階的に進める」という発想が学校内に共有されたこと自体が前進だったと考えています。 ⑤ プロセスをオープンにして関心を喚起 ルールを変えるだけでなく、「なぜ・どうやって変えたか」という過程を可視化することを重視しました。活動の内容や進捗は、Classi、ホームルームでの報告を通じて広く周知。委員会の外にいる生徒からも声が上がる環境になり、関心の輪が少しずつ広がっていきました。 |
| 実現できたこと、できなかったこと |
| ■ 実現できたこと: ・髪型・髪色・アクセサリーの校則見直しが実現: ピアス・髪色・髪型などの表現に関するルールについて、対話会や教員との交渉を経て、校則が緩和されました。具体的には「明確な禁止」から「節度を持つよう配慮」という表現に変更され、生徒の個性や自由が一定程度認められるようになりました。 ・「ルールは話し合って変えていい」という空気が学校に浸透: 全校アンケート、HRでの報告、掲示物による発信を通して、ルールを上から与えられるものではなく、「自分たちで見直せるもの」として捉える雰囲気が広がりました。特に下級生から「自分たちも参加したい」という声が上がるようになったことは、大きな変化でした。 ・教員とのフラットな関係性の構築: 一方的に意見をぶつけるのではなく、教員に背景を尋ねるインタビューや、双方向の対話を重ねることで、「敵・味方」ではなく「対話のパートナー」として関係を築けました。対話会のあとには、教員側からも「もっと生徒と話したい」との声が上がりました。 ・自動車免許取得・アルバイトの自由化: 校則で「原則禁止」とされていた自動車免許の取得とアルバイトについて、個別の届け出制から完全自由化が実現しました。生徒の声が反映され、「学業を最優先」の上で自由化にするという内容に学校の方針が変化しました。 ■ 実現できなかったこと: ・スマートフォンの持ち込み自由化は実現せず: スマホの校内持ち込みについては、紛失や盗撮などのトラブル対応への不安が強く、教員との間で合意に至らず。特に使用場面や管理ルールに関する整理が不足しており、来年度以降の継続検討課題となりました。 ・全校生徒を巻き込む難しさ: 全校に発信はしていたものの、関心が低い生徒や「変わらなくていい」という声を持つ生徒を巻き込むのは困難でした。「どうせ無理」と思っている層にも響くような言葉や仕組みの必要性を痛感しました。提案の即時実現の難しさと、粘り強さの必要性: 対話を重ねても、すぐに校則が変わるわけではなく、いくつかの提案は「継続議論」という形にとどまりました。ただ、教員側と「前向きに検討する」という共通認識を持てたことで、今後への足がかりにはなったと感じています。 |
組織について
| 組織体制 |
| 生徒会長:米田圭吾 ルールメイキング委員長:中北啓 委員会メンバー:15名(1〜3年の生徒から希望者が集まる)+ 担当教員一名 |
| 任命方式 |
| 希望制。参加者は自主的に集まり、学年や所属に関係なくフラットに活動している。 |
| 「顧問/学校」と「生徒自治活動の組織」との関係 | |
| 評価(1~5点) | 5 |
| なぜその評価になるのか | 学校側は、最初から私たちの活動を完全に受け入れてくれたわけではありませんでしたが、提案や対話を重ねるなかで徐々に理解を示してくれるようになりました。生徒の声に耳を傾け、ルールを共につくる姿勢をとってくれたことは、非常に大きな意味を持っています。また、顧問の先生方がファシリテーター役に徹してくださり、生徒主体での議論が尊重される空間をつくってくださいました。学校との「協働」が本当に実現できたと感じています。 |